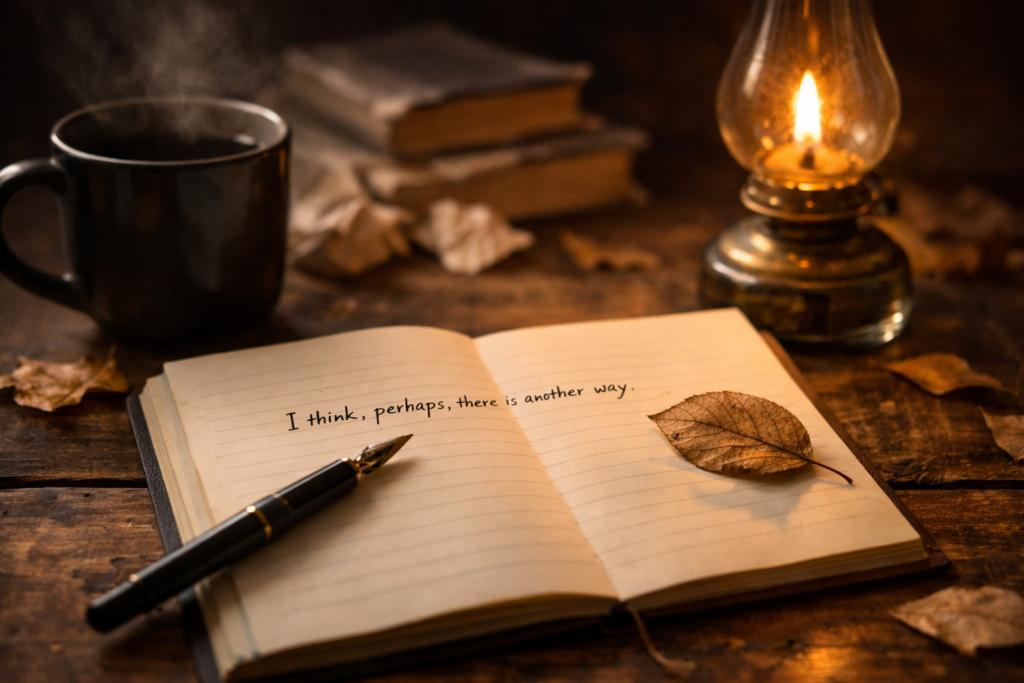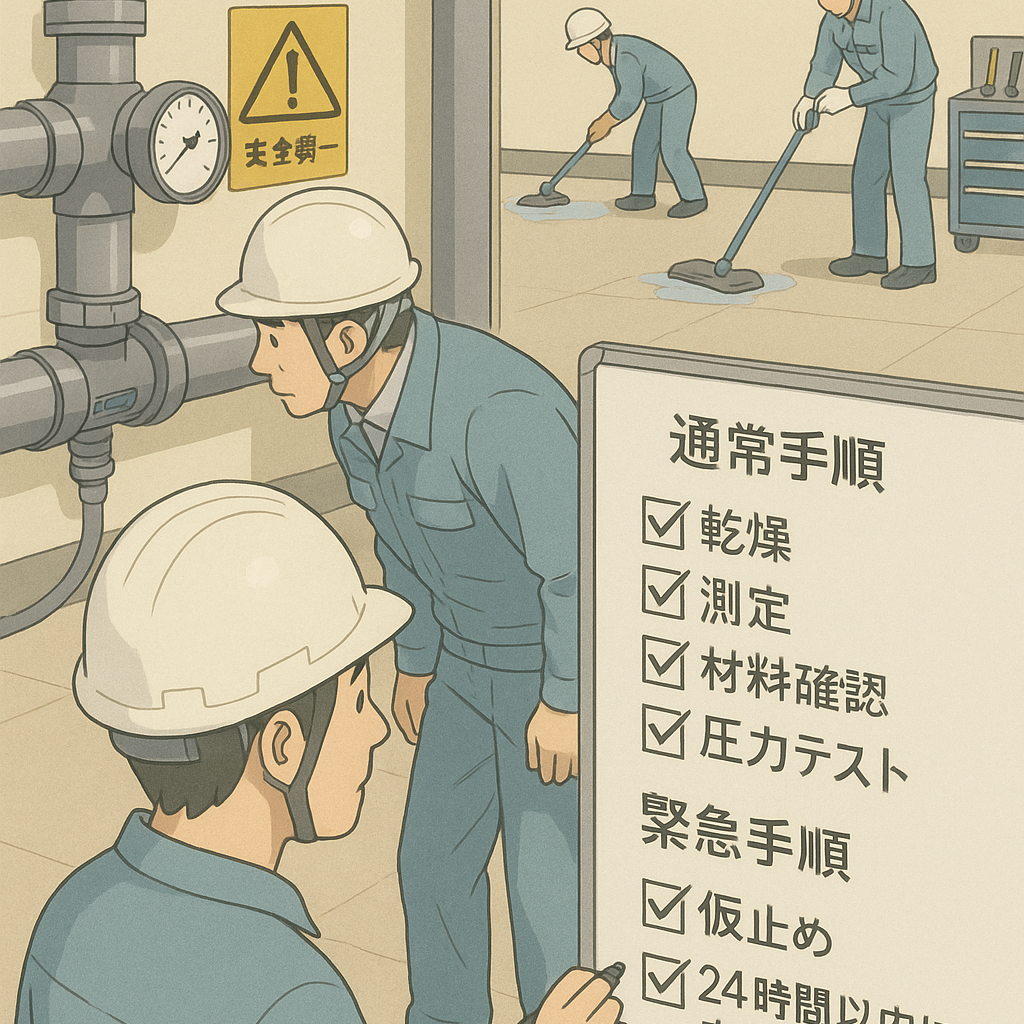文章には、音がある。
読み手の中で鳴る、小さな音だ。
静かなエッセイのあとに、短い挨拶が置かれる。
「おはよう」とか、「いいですね」とか。
それ自体は悪くない。むしろ優しい。
けれど、挨拶のあとに続く言葉が、いつも同じ方向へ流れることがある。
本文の話題に触れているようで触れていない。
問いに答えているようで、問いを持ち去ってしまう。
そして、読んだ人の頭の中に、説明しづらい疲れだけが残る。
ここでは、コメント欄を荒らすための誰かを責めたいわけではない。
ただ、「議論にならない型」が何度も繰り返されると、文章の場は少しずつ痩せていく。
そのことを書いておきたい。
「結果が良ければそれでいい」
もちろん、それが真になる場面もある。
ただ、その一文が置かれた瞬間、本文が扱っていたもの――
プロセス、仕組み、検証、再発防止、契約、評価指標――
そういう“地味だけど大事なもの”が、ふっと消える。
結果論は、便利だ。
便利すぎて、たいていの問いを黙らせてしまう。
「権限がない人が言うべきではない」
これも、現場のリアルとして理解できる。
でも、その言葉が続くと、場はこうなる。
問いを立てる人が黙り、
数字を集める人が黙り、
改善案を置く人が黙り、
最後には、誰も書かなくなる。
権限は大事だ。
ただ、権限の話だけが前に出ると、思考は止まり、議論は終わる。
止まった議論は、また同じ問題を繰り返す。
「当事者は分かってるけどできないんだ」
これも真実であることが多い。
けれど、その真実は、使い方によっては霧になる。
霧は、傷を見えなくする。
見えない傷は、手当てが遅れる。
当事者のもどかしさを語るなら、
次の一歩も一緒に置いてほしい。
「だから、まずこれをやる」
「この条件なら、ここまでならできる」
霧の中に、道標を一本立てるように。
本や旅や流行や、昨日見たニュース。
話が広がるのは楽しい。
ただ、コメント欄は「舞台」になりやすい。
本文から少し逸れるだけなら問題はない。
でも、逸れ続けると、いつの間にか主役が入れ替わる。
文章の場は、書いた人のものでも、コメントした人のものでもない。
読んで持ち帰る人のものだ。
雑談が主題を覆うと、持ち帰るものが減っていく。
「頭が悪い」「笑いのツボ」
強い言葉は、短く刺さる。
刺さったあとに残るのは、思考ではなく、棘だ。
棘は、文章の場を「正しさの勝負」に変える。
勝負になると、長引く。
長引くと、読む人が減る。
減ったところに、強い言葉だけが残る。
だから私は、コメント欄を「勝負の場」にしたくない。
拍手も罵声も、どちらも音量が大きすぎる。文章の余韻を押しつぶしてしまう。
欲しいのは、もう少し小さな音だ。
本文のどこか一行に指を置いて、「私はこう読んだ」と言える音。
反対なら、反対の理由の隣に、せめて一つの代案を置く音。
その音は派手ではないけれど、読む人の中で長く残る。
短い挨拶は温かい。
けれど、挨拶だけで場は育たない。
結果論だけでは、検証が残らない。
権限論だけでは、工夫が生まれない。
当事者論だけでは、道が見えない。
雑談だけでは、主題が薄まる。
人格の棘だけでは、誰も持ち帰れない。
文章の場は、だれかを言い負かすためにあるのではなく、
読んだ人が明日を少しだけ良くするためにある。
だから私は、ここに残る言葉の形を整える。
必要なら、言葉の数を減らす。
反応が増える仕組みではなく、理解が深まる仕組みを選ぶ。
走る足音が消えたあとに、遅れて聞こえる声がある。
「助かった」という、小さな声だ。
私は、その声が聞こえる場所を、残しておきたい。