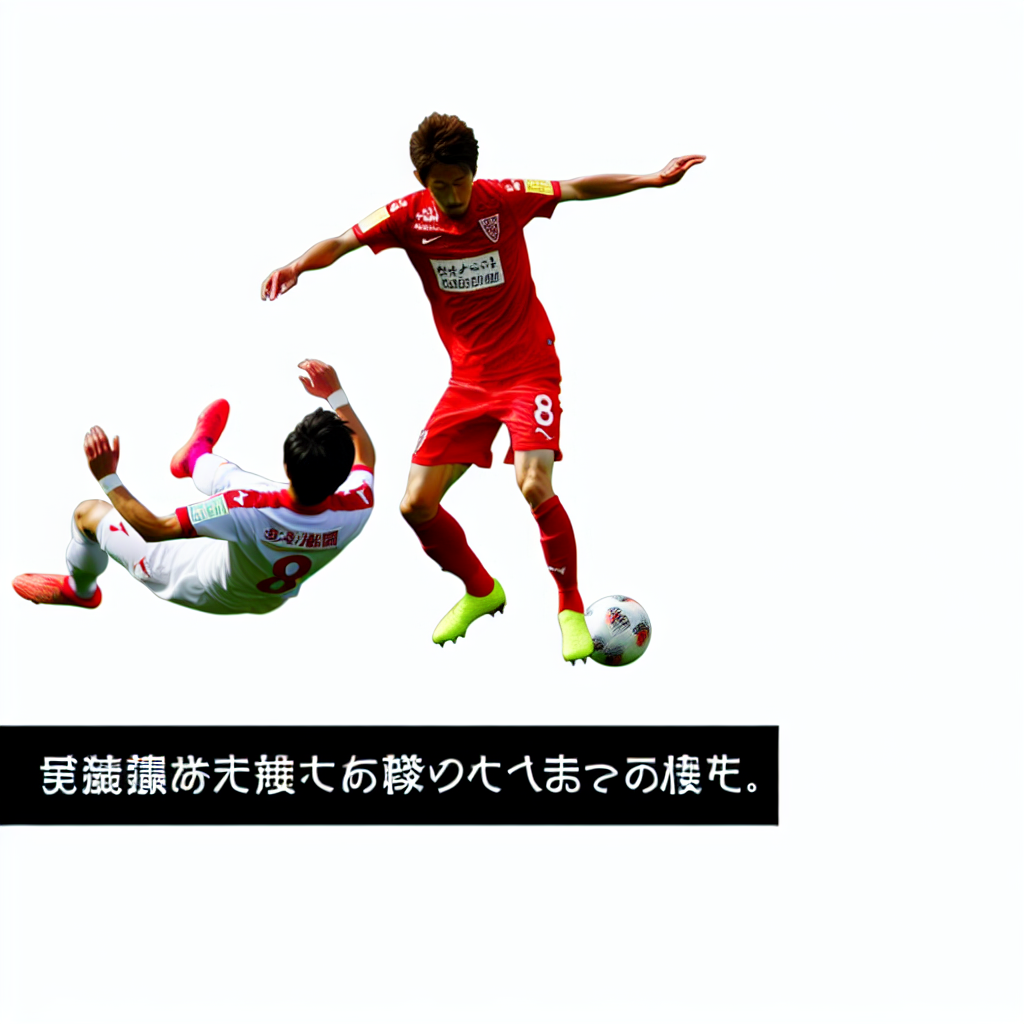ハローワークを漁っていたところ、この求人票を発見。
にじいろ市場求人票
「ハローワーク求人検索より。この求人票の内容は2025年7月6日時点の公表情報に基づいています」
1. 概要と求人の特徴
求人票概要
事業所名:にじいろ市場(群馬県高崎市)
職種:通販のDX化(パートタイム、完全在宅勤務、週4-5日)
勤務場所:自宅(全国応募可、在宅ワーク可、カフェ等も可)
時給:985円
労働時間:週20時間程度(勤務日や時間帯は個人に合わせ相談可、休憩自由)
業務内容:通販サイト運営・SNS運用・プログラム開発・自動化・プロモーション
必須経験・スキル:自力でPC/スマホトラブル対応、プログラミング経験(VBA・RPA歓迎)、PC/スマホ利用
雇用期間:4ヶ月以上(契約更新あり・トライアル雇用あり)
福利厚生:各種保険は条件満たせば加入、有給休暇法定通り
選考方法:書類選考・筆記試験・オンライン面接
2. 障がい者求人としての適正評価
【1】仕事内容・職種と障がい者への配慮
● 求人内容と障がい者への配慮
完全在宅勤務を明言。通院や体調不良時は柔軟に休める体制
重い荷物運びなし、やり取りはLINE/Teams等、通院日の配慮も明記
ノルマなし(目標設定あり)、柔軟な働き方
必須スキルは「プログラミング経験」および「PC/スマホの自力問題解決」
「子育てや家事も職歴とみなす」など、多様性への理解を強調
→ 在宅勤務・障がい特性への配慮は一通り明記されており、一般的な障がい者求人よりも自由度は高い部類です。
● 業務負荷と求めるスキルのバランス
主業務は通販サイト運営・自動化・SNS運用・プログラム作成と専門性が高い
プログラム開発やRPA/VBA等のITスキルは一定レベル以上が必須
PCやスマホのトラブルも「自力で検索解決できる」ことを求めており、一般的な事務職よりはITスキル重視
【2】労働条件・報酬の妥当性
● 時給985円の評価
最低賃金との比較(2025年 群馬県 最低賃金:時給935円前後、全国平均約1000円)
2025年の最低賃金見通しや物価動向を考えると、「985円」は最低賃金ラインギリギリ
一般的な事務補助や軽作業に比べると、求めるスキル(IT/プログラミング)は明らかに高い
業務内容からすると「低水準」と評価せざるを得ない
● 労働時間・働き方の柔軟性
週4~5日・週20時間前後で自由なシフト設計・休憩も自由
通院や体調管理を重視する障がい者にとっては大きなメリット
労働時間は短め(パート)、ただしその分収入面は限られる
● 在宅ワーク求人の相場と比較
IT系在宅ワーク・プログラム補助職(障がい者向け)でも、相場は時給1000~1200円以上が一般的
仕事内容の専門性(通販運営+プログラミング)を考えると、低賃金と評価される可能性が高い
【3】求める人物像・企業の意図
「一般企業で働いたことがある方優遇」や「自分で調べて解決できるITリテラシー」など、即戦力的な人材を希望している
一方で「子育てや家事も職歴とみなす」「体調不良や通院に理解」など、ダイバーシティ・インクルージョン志向は明示
しかし報酬水準がスキル要求と釣り合っていない点は、即戦力・高スキル人材の応募ハードルを上げている
3. 労働市場の現状と求人の適正性
2025年時点での障がい者在宅求人市場は拡大傾向
在宅IT・DX系の求人は障がい者雇用でも増加中だが、「業務の高度化」と「賃金の据え置き」が社会課題に
この求人も、仕事内容に対して報酬が追いついていない典型例。
「スキルのある障がい者」にとって、もっと高条件の求人も十分に選択肢となる時代
一方、柔軟な労働時間・在宅可・通院配慮など、非金銭的メリットは高い
4. 総合評価と結論
【評価まとめ】
在宅・障がい者配慮の姿勢:高評価
柔軟な働き方・休憩・体調配慮:高評価
仕事内容・スキル要件:やや高度
報酬水準:仕事内容に対し「不十分・低水準」
企業の求める人物像:即戦力志向もあり、応募ハードルはやや高い
【結論・求人の正当性】
形式的には障がい者雇用として「正当」だが、報酬水準と業務負荷のバランスに課題
スキルある障がい者にとって、同等以上の好条件求人も多いため、やや厳しめの条件
「未経験可」の姿勢は薄く、実質的には「プログラム実務経験者」向け
5. 今後の障がい者雇用に向けて(意見)
真に多様な人材を活かすには、「在宅・柔軟性」だけでなく、専門スキルには報酬面の厚遇が不可欠
「スキルや経験がある障がい者は、より良い待遇を求めてよい」という時代にあり、企業側にも報酬水準見直しが期待される
一方、働きやすさや配慮を最優先にしたい方にとっては、選択肢のひとつとして検討余地はある
参考文献・調査データ
厚生労働省 障がい者雇用状況(2024-2025年動向)
最低賃金(2025年目安)
まとめ
この求人は、「在宅・柔軟・障がい者配慮」は評価できるものの、専門性の高さに対して報酬が低く、現代の障がい者労働市場の水準には届いていない。
今後は、専門スキルには相応の待遇を提示し、「誰もが無理なく、正当に評価されて働ける」環境づくりが不可欠といえる。
所感
障がい者雇用の現場には、「ゆるい条件」を掲げて一見働きやすそうに見せながら、実際には高い専門性や幅広い対応力を求める求人が依然として存在します。本求人もその一例であり、
「低賃金・短時間」という一見やさしい条件の裏に、実は難易度の高い業務や責任を求められる構造が見え隠れします。
障がい者の就職状況の“足元を見た”採用が未だ残る現実に、正直なところ暗い気持ちを抱かざるを得ません。
働きやすさと適正な評価・待遇が両立する社会の実現には、求人票の表現や条件の透明性、そして企業の姿勢そのものが改めて問われていると強く感じます。
【追記】ファクトチェック:業務内容と報酬水準の妥当性
今回の求人「通販のDX化(ECサイト運営・SNS運用・プログラム自動化等)」について、2024~2025年の最新求人サイトおよび公的データをもとに、時給水準が妥当かどうかを検証しました。
障がい者向けIT・EC運営・プログラム補助求人の時給相場
- 在宅・ECサイト運営・SNS運用など:時給1,100~1,400円
- プログラム自動化(RPA・VBA等)経験者:時給1,200~1,600円
- 求人例や条件は下記リンクより直接ご覧いただけます。
【求人サイト(障がい者向け)】
atGP(在宅勤務・リモートワーク配慮の求人一覧)
一般在宅パート・業務委託の時給相場
- EC運営・SNS運用・自動化ツール作成:時給1,200円~2,000円超
【求人サイト(一般・在宅・フリーランス系)】
Indeed(ECサイト運営 在宅 求人例)
Indeed(SNS運用 在宅 求人例)
クラウドワークス(EC・IT系パート/業務委託)
厚生労働省の最新調査
- 障がい者パート全国平均時給(2023年):1,027円
- IT・事務系では1,100円超の案件が増加傾向
- 出典:厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」
厚生労働省 障害者雇用状況報告書及び記入要領等
令和6年 障害者雇用状況報告(集計結果PDF)
総括
今回の求人が提示する「時給985円」は、業務内容・必要スキルから見て全国相場より明らかに低い水準です。
同様の仕事内容であれば時給1,200円以上が一般的な相場であり、記事の指摘は公的データや求人情報と一致しています。
本記事で用いたデータや求人情報はすべて、上記URLより誰でも閲覧可能です。
※求人相場・データはいずれも2024~2025年7月時点での公開情報をもとにしています。